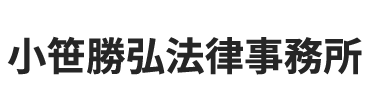不倫相手が妊娠したときの注意点!適切な対応や請求される慰謝料額について
弁護士 金井啓

一般の方々に、わかりやすく法律の知識をお届けしております。
難しい法律用語を、法律を知らない人でも分かるような記事の作成を心がけています。
不倫慰謝料に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。
「不倫相手を妊娠させてしまった…」という場合、一体どうすればいいのでしょうか?不倫が発覚するだけでも互いのパートナーから慰謝料請求を受けるリスクがありますが、妊娠をしているとさらに問題は複雑化し、請求額も大きくなる可能性が高くなります。
不倫相手への身心の配慮も必要となりますし、当記事の内容を参考にしつつ適切な対応を心がけること、可能なら弁護士に相談することをおすすめします。
不倫相手が妊娠しているという事実は、配偶者から受ける慰謝料請求に大きな影響を与えます。
慰謝料請求においては、不倫によって配偶者が受けた精神的苦痛の大きさが重要な要素となりますが、妊娠は「不倫関係の深刻化」を示すものとして、精神的苦痛をより大きくしたと判断される可能性が高いからです。
具体的には、以下の2点に対する影響が考えられます。
- 慰謝料額の増額・・・不倫関係がより深い関係に進展したことを示唆し、配偶者に与える精神的苦痛もより大きいと判断されやすい。そのため一般的な不倫における慰謝料額の相場に比べて金額が大きくなる可能性が高い。
- 慰謝料請求の正当性が増す・・・妊娠は不倫の事実を示す証拠となるため慰謝料請求の正当性がより増す。
なお、不倫を原因とする慰謝料の金額はさまざまな要因が絡み合って定まりますので一定額ではありませんが、相場としては「数十万円~300万円」と説明することができます。
妊娠をしている場合であればもう少し全体の額が大きくなると予想され、「100万円~500万円」になることも十分に考えられます。
妊娠の有無のほかには以下の事由が慰謝料の額に影響を与えます。
| 慰謝料が増額するその他の事由 | |
| 不倫期間 | 期間が長ければ長いほど配偶者が裏切られ続けていた期間が長くなり、精神的苦痛も大きくなるため、慰謝料が増額される傾向にある。 |
| 不倫の回数 | 回数が多いほど、不倫関係が一時的なものではなく、継続的な関係であったことを示し、配偶者への裏切り行為の悪質性が高まると判断されるため、慰謝料が増額される傾向にある。 |
| 婚姻期間 | 婚姻期間が長ければ長いほど夫婦間の信頼関係が深く、不倫によって失われたものの大きさが強調されるため、慰謝料が増額される傾向にある。 |
| 子どもの有無 | 子どもがいる場合、不倫による精神的なダメージが大きくなりやすく生活への支障も起こり得ることから、慰謝料が増額される傾向にある。 |
| 発覚後の態度 | 反省の態度が見られない場合や配偶者を侮辱するような言動があった場合、行為の悪質性が高まると判断され、慰謝料が増額される傾向にある。 |
| 配偶者の精神状態 | 不倫によって配偶者がうつ病などの精神疾患を患った場合、治療費や慰謝料が増額される傾向にある。また、その結果仕事を休むことになればその損失を補填するためにも賠償額が大きくなる。 |
不倫相手の配偶者からの請求額も大きくなる
不倫相手にも配偶者がいる場合、その方からも慰謝料の請求を受ける可能性があります。
不倫による精神的な苦痛を受けるのは自身の配偶者のみならず、相手方の配偶者も同じだからです。
実際、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されるのも珍しいことではありません。また、請求額の考え方も自身の配偶者から請求を受ける場合と変わりはありません。
妊娠の疑いがあるときの対応
不倫相手が本当に妊娠をしているのなら、早めに対処する必要があります。
そこで、妊娠の疑いが生じたときは以下の対応を進めていきましょう。
- まずは事実確認
・・・妊娠をしているのかどうか、事実を確認することが最優先。妊娠の可能性を告げられた場合でも責任逃れをしようとせず冷静に状況を整理していく。以下の方法で事実確認を行う。- 妊娠検査薬(簡易的な検査なら市販のものでも可能)
- 産婦人科での受診(妊娠検査薬で陽性が出たときは医療機関で正確な診断を受ける)
- 不倫相手と今後の方針を話し合う
・・・相手の意見を尊重し、互いの今後の生活のことも考慮してこれからの対応を検討。- 出産・中絶の判断
- 出産をする場合は認知をするかどうか、養育費をどうするかについて話し合う
- 専門家への相談
・・・妊娠の疑いがあるとき、法的な問題については弁護士に相談するのが有効。
逃げた場合の問題や法的なリスク
妊娠の疑いが生じた際に責任を回避しようと逃げたり、連絡を絶ったりする行為は、さまざまな問題や法的なリスクを伴います。
第一に、不倫相手が不安・孤独感を抱えることになり、大きな精神的苦痛を受けることになります。
そしてその結果、不倫相手から慰謝料請求を受ける危険性がありますし、より事態が深刻化するリスクが高まってしまいます。
中絶の強要で不倫相手から慰謝料請求を受けることも
妊娠が発覚した場合、2人で話し合い、中絶という選択肢も出てくるかもしれません。
当事者間でしっかりと話し合い決めた結論であれば法的な問題はありませんが、一方的に中絶をするよう押し付けてはいけません。
不倫相手が中絶を望んでいないにもかかわらず中絶を強要した場合、そのことを理由に不倫相手から慰謝料を請求される可能性があります。特に、「中絶をしなければ痛い目にあわす」などと脅す、殴る蹴るなどの行為により中絶を迫る、といった悪質な行為を伴うケースではそのリスクが高まります。
自身の保身ばかり考えるべきではありませんし、結果的にその行為が保身につながらない可能性もあるため、真摯に対応するよう心がけましょう。具体的な対応方法、解決策について考えるときは弁護士も利用すると良いです。
中絶を選択するときの注意点
中絶も視野に検討を進める場合、以下の点にご注意ください。
「妊娠22週未満」がタイムリミット
中絶手術に関しては母体保護法という法律でルールが定められており、そこでは「人工妊娠中絶」について次の定義が置かれています。
この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。
引用:e-Gov法令検索 母体保護法第2条第2項
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0100000156
そして「胎児が母体の外で生命を保続できない時期」は、次のように考えられています。
法第2条第2項の「胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期」の基準は、通常妊娠満22週未満であること。
なお、妊娠週数の判断は、指定医師の医学的判断に基づいて、客観的に行うものであること。
引用:厚生労働省 母体保護法の施行について
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta9675&dataType=1&pageNo=1
つまり、基本的には妊娠期間が22週を経過するまで(妊娠21週と6日まで)に決断しなければいけません。
この期間を過ぎると中絶ができなくなりますし、また、時期が遅くなると母体への負担も大きくなるため早めの決断が重要になってきます。
判断のポイント
中絶をするかどうか、その判断においては以下のポイントを踏まえて慎重に考える必要があります。
| 考慮すべきこと | 内容 |
| 母体の健康状態 | 中絶手術は身体的な負担・リスクを伴うため、相手方の健康状態などを踏まえて判断すべき。 |
| 精神的な影響 | 中絶そのものが精神的なストレスとなり、トラウマになる可能性もある。この点にも配慮し、そうならないようなフォローが必要。 |
| 経済状況 | 中絶には費用がかかるが、出産やその後の育児費用の方が大きいため、互いの経済状況も鑑みて考える必要がある。 |
| 家族や友人のサポート | 出産をする場合は、子どもを育てていけるかどうか、その際相談に乗ってくれる人物やサポートしてくれる人物がいるのかどうかが重要。 |
出産を選択するときの注意点
出産を選択するのなら、生まれてくる子どもの将来、そして自分自身や配偶者、不倫相手、それぞれの人生を大きく左右することになります。
法的な問題、そして経済的な問題なども考えながら慎重に進める必要があります。
認知の手続き
不倫関係で生まれた子どもは、法律上は「非嫡出子」と呼ばれ、自身と子の間に法律上の親子関係は自動的には発生しません。
父子関係を成立させるには、父親がその子を「認知」しなくてはなりません。
| 「認知」について | |
| 制度の概要 | 認知とは、父親が「自分の子どもである」と法的に認める手続き。認知により法律上も自身の子となり、親子関係が発生する。 |
| 認知することの影響 | 認知をすることで「戸籍への記載」がなされ、戸籍謄本等を取り寄せたときに子どもの存在が知られる可能性がある。 また、認知した子は「法定相続人になる」こともできる。 |
| 認知の手続き | 認知をする場合、市区町村役場に「認知届」を提出する。これは任意に基づく手続きであるが、認知をめぐってトラブルになり不倫相手が家庭裁判所に申し立てを行うこともある。これにより強制的に認知が成立するケースもある。 そのほか、自身の死後に認知をすることも可能で、その場合は遺言書に子を認知する旨を記載する。 |
養育費の支払い
子どもを出産することになれば、子どもを育てるための費用がこれから発生することになります。
この「養育費」についても考えなくてはなりません。
| 「養育費」について | |
| 養育費の金額 | 養育費の金額は、父母の収入や子どもの年齢、生活水準などを考慮して決定する。具体的な金額は、家庭裁判所の調停や審判、あるいは父母間の協議によって定まる。 一般的には、家庭裁判所が作成した「養育費・婚姻費用算定表(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)」が参考にされる。 |
| 養育費の支払方法 | 養育費の支払方法についても父母で話し合って決めることができるが、毎月定額を支払う方法が一般的。ほかには、経済力があれば一時金で支払う方法などもある。 |
| 養育費の支払いを怠った場合 | 養育費の支払いについて取り決めを交わしたにもかかわらず、きちんと支払いが履行されない事案が多い。この場合、相手方から強制執行の手続きを取られる可能性がある。強制執行がなされると裁判所の命令に基づく給与や預金、不動産などが差し押さえられる。 |
中絶をする場合にもさまざまな事柄を考慮しないといけませんし、重大な事項であることに変わりはありません。
しかし出産を選択すると長期にわたり各当事者の親としての法的責任が生じます。子の人生についても考えていく必要があり、より慎重な判断が求められます。
慰謝料請求のことや、中絶・出産をする場合の法的な問題などについては弁護士もサポートすることができますので、不安があるときはまずご相談いただければと思います。
横浜クレヨン法律事務所では・・・
浮気・慰謝料問題への対応に非常に力を入れています。婚姻関係の破綻が争点になった事例も数多く取り扱ってきました。
慰謝料問題に不安がある方、弁護士が親身になってサポートいたします。LINEを始めとした各種の無料相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。