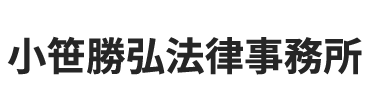慰謝料を払わないといけない要件|不倫をした方がチェックすべきポイント
弁護士 金井啓

一般の方々に、わかりやすく法律の知識をお届けしております。
難しい法律用語を、法律を知らない人でも分かるような記事の作成を心がけています。
不倫慰謝料に関する様々な悩みを持つ方々のために、当ホームページは有益な情報を提供いたします。
「不倫がバレると慰謝料を支払わないといけない」と考える方も多いですが、厳密に慰謝料の支払い義務を考えるときは、法律上の要件に着目してひとつひとつ評価していくことが大事です。
そこで当記事では、不倫をしてしまい慰謝料の支払いについて不安を抱く方に向けて「どんな場合に慰謝料を支払わないといけなくなるのか」ということを解説していきます。
少しでも人の嫌がることをすれば慰謝料の支払いが必要になるということではありません。
不倫においては「婚姻共同生活における平和の維持」という権利・法的利益を侵害することが根本の問題です。
そしてこの権利や利益があるといえるためには、前提として結婚をしていないといけません。
そこで不倫に際して慰謝料の支払い義務が生じるためには、原則として「結婚をしていること」が必要です。
お付き合いをしている彼氏・彼女がいる状況で他の方と関係を持ったとしても、基本的に慰謝料の支払い義務は生じません。
また、そのお付き合いをしている方とその後結婚をしたとしても、結婚前の不貞行為を理由に慰謝料を支払う必要はありません。
ただ、事実上の夫婦関係にある方が浮気をして、慰謝料の支払い義務が生じることはあります。
内縁の夫・内縁の妻など、内縁関係にあるときでも夫婦としての実態があるなら法律上の夫婦と同視することができるのです。
内縁関係にあるときはどこから夫婦と評価するのか明確な線引きをするのが難しいですが、少なくとも「婚姻の意思を持っていること」と「夫婦としての共同生活があること」が必要になるでしょう。
※ただしこのときでも夫婦に適用されるすべての法制度が同等に適用されるわけではない。
相続など、婚姻届を提出して法律上の夫婦になっていることを条件とする例もある。
婚姻関係が破綻していると要件は満たさない
もし結婚をしている方が不倫をしても、その時点ですでに婚姻関係が破綻していたのであれば、不貞行為による不法行為が成立しないと考えられています。
ただし、婚姻関係の破綻は離婚とは異なり事実上の状態であることから、判定が容易ではありません。
個別に状況を見る必要があり、婚姻生活の様子、その他様々な事情を考慮して自己に有利な主張をしていくことが大事になってきます。
例えば次のような事情は婚姻関係の破綻を判断する上でポイントになってきます。
- 被害者側が配偶者との生活継続を望んでいるかどうか
- 離婚の意思があったかどうか
- 別居をしていたかどうか
- 肉体関係があったかどうか
- 家族旅行やイベント等を行っていたかどうか など
離婚の意思があって数年間別居をしていたようなケースだと、慰謝料の支払い義務を負う可能性は低くなります。
逆に、夫婦仲が多少悪かったとしてもそれだけで慰謝料の支払いを回避できることにはなりません。
結婚生活が長いと慰謝料は大きくなりやすい
結婚をしていることが慰謝料発生の前提条件となりますが、結婚をしているときは、結婚生活の長さにも着目しましょう。
慰謝料の大きさは人それぞれ、ケースバイケースで異なるところ、結婚生活が長いほどその額は大きくなる傾向にあるからです。
結婚して3年目の夫婦と結婚して20年目の夫婦がいるとき、その他の条件がまったく同じであれば、後者の方が慰謝料の大きさは大きくなる傾向にあります。
要件②肉体関係があった
「不倫」や「浮気」という言葉は一般用語であって厳密な定義がありません。
人それぞれ捉え方が異なります。そこでこの言葉に縛られるべきではなく、法的な解釈を知っておくべきです。
そして法律上は「不貞行為」が不法行為を構成するとされ、不倫や浮気の内容を鑑みて不貞行為と呼べるかどうかを評価していきます。
ここで重視されるのは肉体関係の有無です。配偶者以外と性的関係を持つことが不貞行為と評価され、慰謝料の支払い義務を生じさせます。
ただし不貞行為は必ずしも肉体関係に限られません。
次のような行為も広く不貞行為に含まれ得ることから、慰謝料支払い義務の有無について考えるときは「不貞行為に該当する行為をしたかどうか」についてよく考える必要があります。
- 性行為に類似する行為
- 同棲すること
- その他、配偶者との婚姻関係を破綻させる蓋然性がある異性との交流や接触
判例上も、「第三者と配偶者が肉体関係にあることが違法性を認めるための絶対的要件ではない」旨を判事しています(東京地裁H17.11.15)。
また、「不倫相手との婚姻を約束して関係を続け、さらに配偶者との別居・離婚を求め、キスをした」という事実から不法行為が構成されると判事された例もあります(東京地裁H20.12.5)。
このように、肉体関係を持たなくても慰謝料の請求が認められる可能性はあるということは覚えておくと良いでしょう。
自分の意思によらないときは要件を満たさない
不貞行為かどうかは、肉体関係の有無から機械的に判定するわけではありません。
当然、自らの意思で肉体関係を持ったということが責められるべきであって、自分の意思によらず肉体関係を持ったときは責任追及をすべきではないと考えられます。
例えば性的暴行は被害者の方が望んだ結果ではなく、これを理由に不貞行為が認められるべきではありません。
逆にいえば、より積極的に自分から不貞行為をはたらいたという事情があれば帰責性はより大きくなり、支払うべき慰謝料も大きくなります。
頻度が高く期間が長いと慰謝料は大きくなりやすい
1度の肉体関係でも、数年に及ぶ複数回の肉体関係でも、不倫であることに変わりはありません。
ただ両パターンにおける被害の大きさは同じではありません。
そこで関係を持った頻度が高いほど、期間が長いほど、慰謝料は大きくなる傾向にあります。
要件③精神的なショックを受けている<
不倫を理由とする慰謝料の支払い義務は、民法第709条および第710条の規定を根拠に発生します。
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
引用:e-Gov法令検索 民法第709条・第710条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
ここでいう「不法行為」は不貞行為、「損害賠償」は慰謝料の支払いを指します。
710条で定められているように、賠償すべき内容は財産に関するものに限られず、例えば精神的なショックに対しても賠償はされるべきなのです。
この精神面の損害に対する賠償金を慰謝料と呼んでおり、不倫により精神的なショックを受けていることが慰謝料発生の要件でもあるといえます。
そしてショックの程度が大きいほど被害額は大きくなりますので、賠償すべき額も大きくなります。
不倫後の結果に応じて慰謝料は大きくなる
精神的なショックの有無や大きさについては正確に測ることができません。
そのため双方の主観に基づいて「ショックはとても大きく1,000万円ほどの被害額に相当する」「大したショックはないはずだから慰謝料は発生しない」などと主張しても裁判上は認められません。
当事者間の示談交渉の場においては自由に話し合って支払い額を定められますが、最終的な解決手段である裁判では法的な観点で被害額の有無・大きさを評価します。
そこで過去の事例も参照しつつ、おおむね「数十万円~300万円」程度の慰謝料額になるのが相場とされています。
具体的な金額は、不倫による結果に応じても変動します。例えば次のような被害は慰謝料の額に大きく影響を与えます。
| 離婚をすることになった | 不貞行為が発覚したことをきっかけに夫婦仲が悪化し、離婚をすることになれば、離婚をしないときに比べて被害が大きいと評価でき、慰謝料の額も大きくなる。 |
| 躁鬱状態になった | 病院で躁鬱状態にあることが認められれば大きな精神的苦痛を受けたことが認められやすく、賠償額も高額になりやすい。 |
| 子どもがショックを受けて不登校になった | 不倫がきっかけで夫婦仲が悪化し、その結果、子どもも精神的に不安定になってしまい、不登校になってしまうこともある。この結果についても精神的損害の1つとして含められると考えられる。 |
| 不倫相手との間に子どもが生まれた | 不倫相手との間に子どもが生まれたという事実も精神的苦痛の大きさにつながり、慰謝料を大きくする要因となる。 |
| 周囲の人からの風評被害を受けた | 不倫関係が近隣の人、知人などに知られて風評被害を受けているとき、その風評被害による精神的苦痛も賠償すべきであり慰謝料の額に影響を与える。 |
要件④時効で権利が消滅していないこと
多くの場合、上記3つの要件を満たすことで慰謝料の支払い義務が発生します。
ただ、被害者側に慰謝料の請求権が生じたとしても、いつまでもその権利を行使しないときは時効により消滅します。
法律上、消滅時効という制度が設けられており、一定期間が経過すると権利は消滅する仕組みが採用されているのです。
慰謝料請求権は不法行為に基づく損害賠償請求権と同じですので、請求をされても次の期間が経過しているのなら時効消滅を主張できます。
- 不貞行為の事実を知ってから3年間
※不倫相手の配偶者については不貞行為の事実に加え「請求先」も知ってから3年間 - 不貞行為の事実があってから20年間
※不貞行為について認識しないまま20年間過ぎても時効消滅する。
時効の「更新」に注意
上記の期間が経過していれば、不倫をした方は「慰謝料を請求する権利はすでに消滅しているから、支払いには応じない」と正当に主張することができます。
ただし、消滅時効の期間は特定の行為によって再スタートすること(時効の更新と呼ばれる。)もありますし、一定期間時効が成立しなくなること(時効の完成猶予と呼ばれる。)もあります。そのため下表に挙げる行為があったときには要注意です。
| 裁判上で請求を受けた | 慰謝料請求訴訟を提起されると、その間、時効の完成が猶予され、訴訟中は時効による消滅は起こらない。 判決や和解があると、その時点から新たに時効が進行を始める。 |
| 内容証明郵便により催告を受けた | 内容証明郵便によって慰謝料の支払いを催告されたとき、そこから6ヶ月は時効の完成が猶予される。 ※催告により時効完成が猶予されるのは1回に限る。 |
| 慰謝料の支払い義務を認めた | 慰謝料の支払い義務があることを認めたとき、「債務承認」があったとして、時効期間はそこでいったんリセットされる。 |
以上を踏まえると、
結婚をしているにも関わらず(要件①)、配偶者以外と肉体関係を持ち(要件②)、配偶者に精神的苦痛を与えた(要件③)ときは、消滅時効が完成しない間(要件④)、慰謝料を支払わないといけません。
ただし自動的に支払い義務が生じるわけではありません。上記要件を満たした上で、話し合いにより支払うことを約束する、あるいは裁判で支払うべきことが命じられると、支払いが義務になるのです。
そこで、要件を満たすかどうかだけでなく交渉力や法的な知識も重要といえます。
法律のプロである弁護士に相談し、交渉を代わりにしてもらうことで、その支払い義務を回避できたり支払うべき金額を小さくできたりするかもしれません。
横浜クレヨン法律事務所では・・・
浮気・慰謝料問題への対応に非常に力を入れています。婚姻関係の破綻が争点になった事例も数多く取り扱ってきました。
慰謝料問題に不安がある方、弁護士が親身になってサポートいたします。LINEを始めとした各種の無料相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。